
子育て世帯にとって最も気になるテーマのひとつが「教育資金!」
といった疑問を抱く方も多いでしょう。
おさかな自身は長男・長女を育てる中で、「学資保険に入って安心…と思ったら損してしまった」といった経験をしました。
現在は学資保険ではなく、投資信託(全世界株式インデックス)で積立を継続中。
“リアルな失敗と学び”もふまえて、この記事では「教育資金の全体像」と「わが家の実例」を紹介します。最後までお読みいただくことで、教育資金の考え方がより明確になるはず。
教育資金はいくら必要?(データで把握)
文部科学省の「子どもの学習費調査」(令和5年度)などによると、学校種別・公立/私立別の年間学習費は次のようになります。
| 学校種別 | 公立(年間) | 私立(年間) |
|---|---|---|
| 幼稚園 | 約18.5万円 | 約34.7万円 |
| 小学校 | 約33.6万円 | 約182.8万円 |
| 中学校 | 約54.2万円 | 約156.0万円 |
| 高校 | 約59.8万円 | 約103.0万円 |
さらに、大学(4年間)にかかる費用の平均は以下の通りです:
- 国公立大学:約481万円(入学費+4年間の在学費)
- 私立大学(文系):約690万円
- 私立大学(理系):約822万円

もし私立大学だったら月3.8万円も貯金が必要に!
また別のデータでは、大学4年間の学費は以下の通りとされています:
- 国公立:約243万円
- 公立:約255万円
- 私立:約469万円
出典:進学ネット記事(スタディサプリ)
(※こちらは授業料・入学金換算ベースの推計値として参考になります)
幼稚園〜大学までのトータル費用例
文部科学省「子どもの学習費調査」(令和5年度)および日本政策金融公庫のデータを組み合わせた、進路別のトータル目安は下表のとおりです:
| 進路パターン | 幼〜高校までの総額 | 大学(国公立) | 大学(私立文系) | 大学(私立理系) | 総額(大学含む) |
|---|---|---|---|---|---|
| 全て公立 | 約596万円 | 481万円 | — | — | 約1,077万円 |
| 小〜高校公立+大学私立文系 | 約596万円 | — | 690万円 | — | 約1,286万円 |
| 小〜高校公立+大学私立理系 | 約596万円 | — | — | 822万円 | 約1,417万円 |
| 全て私立文系 | 約1,976万円 | — | 690万円 | — | 約2,666万円 |
| 全て私立理系 | 約1,976万円 | — | — | 822万円 | 約2,798万円 |

大学まで含めると、思っている以上にかかる可能性があるよね💦
平均と実際の差
ただし、これらはあくまで平均値(目安)です。
統計では、全額を親が負担するケースがある一方で、奨学金・アルバイト・補助等を活用する家庭もあり、負担の実態は多様です。

大切なのは「自分たちは教育費をどこまで負担するか?」という方針を明確に持つこと!
おさかな家の教育資金方針(実例)
学資保険を契約した当初
長男・長女それぞれに 月1万円ずつの学資保険をかけていました。最初は安心感があって、これで一件落着!と思っていましたが…

本当にこの決断でいいのかな?
と不安に駆られて、Youtubeやインターネットで調べるうちに、利回りやインフレリスクが気になってきました。
損切りの経験
結果として、3カ月で解約。その際の損失は2人分なので、約6万円でした。

正直、大ショック!
でも「早く気づけてよかった」と今では前向きな学びにつながっています。
現在の方針 ― 投資信託で積立
現在は、長男・長女それぞれに 月1万円ずつをオルカン(全世界株式インデックス)で積立中。
学資保険から投資信託への切り替えは、元々運用していた資産に、まとまった資金を入れました。正確に「教育資金」と線引きしていませんが、子供たちが生まれた月から積立している想定で管理しています。
なので18年後にはそれぞれ、約216万円+運用益になる見込みです。
家庭のスタンスとしては、
「教育費の全額を親が負担するのではなく、最低限のサポートをする」
という方針にしています。
教育資金の準備方法(3つの選択肢)
1、学資保険
→ 保険機能など安心感はあるが、初期は元本割れし流動性・利回り共に低く、インフレには弱い。
2、投資信託(積立)
→ 長期でのリターンを期待できるが、価格変動リスク(元本割れリスク)あり。
おさかな家はこちらを選択中
3、貯金(現金)
→ 流動性が高く元本割れもないので安心だが、利息ではほぼ増えずインフレリスクに対応できない。
それぞれにメリット・デメリットがありますので、ご家庭のリスク許容度や目的に合わせて選ぶのが大切です。
(次回記事では、「学資保険 vs 投資信託」を数字で比較して解説予定です!)
まとめ
- 教育資金は「平均値を参考にしつつ、家庭の方針を持つこと」が重要。
- おさかな家は「学資保険での失敗を経て、投資信託で積立へ切替」という経験を活かしています。
- 教育費の負担は家族それぞれの考え方に応じて。平均に惑わされず、自分たちの支援ラインを話し合うことが第一歩です。
この記事が同じ子育て家庭で悩む方の参考になれば嬉しいです🎶
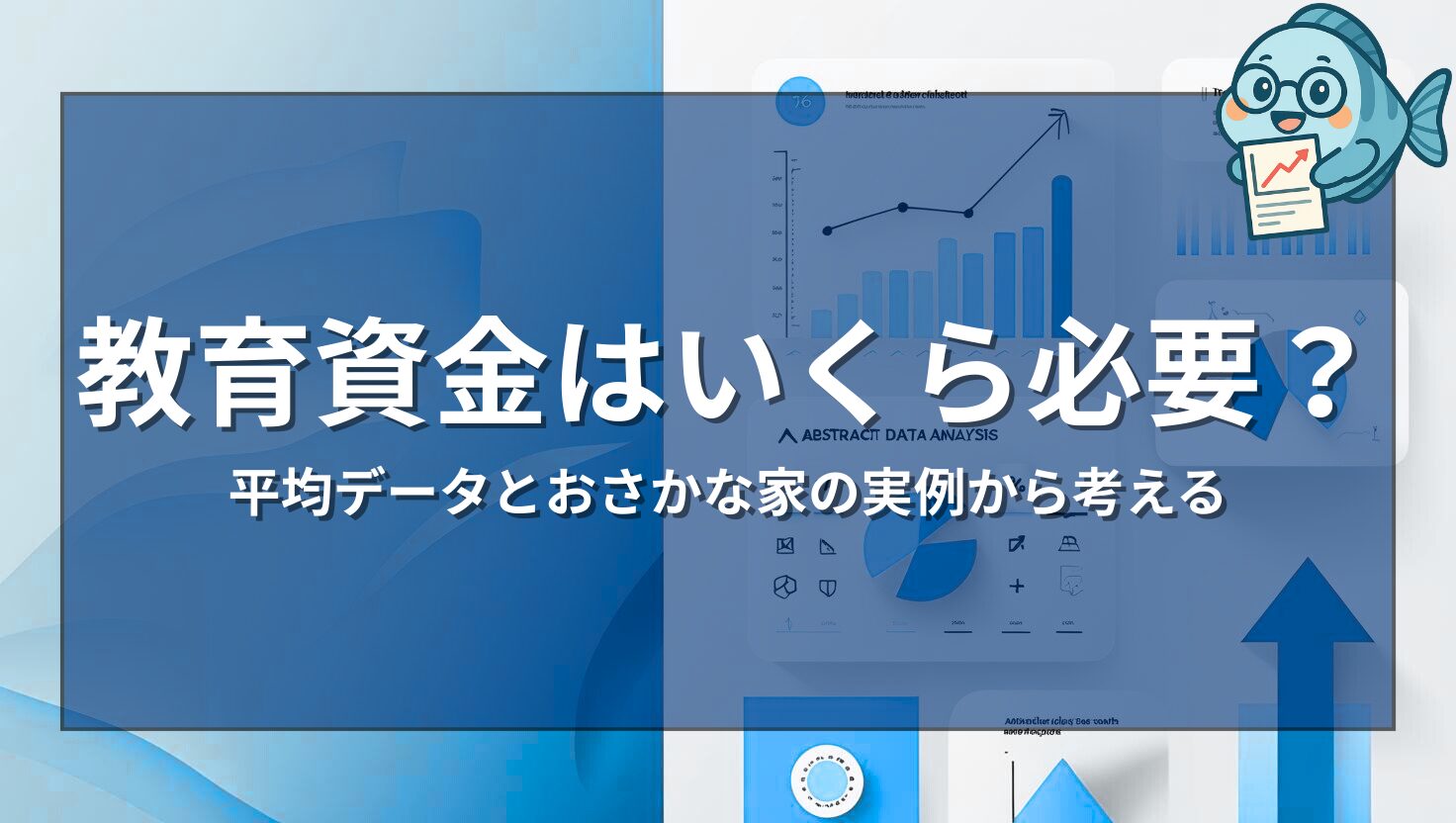
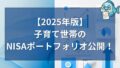

コメント