- 個別株は難しそう…
- 投資信託だけじゃダメなの?
- 新NISAで何に投資してる?
個別株か?投資信託か?で迷っていませんか?

こんにちは!おさかなです
おさかなは借金33万円・貯金ゼロからスタートし、家計改善とNISAの活用で運用額600万円を突破、含み益は100万円超えを達成しました。
この記事では、実際におさかなが運用している
1, 三菱商事・信越化学などの個別株(高配当株投資)
2, eMAXIS Slim 全世界株式などの投資信託(インデックス投資・積立投資)
をどう組み合わせているか、リアルな損益・購入タイミング・リスク管理の工夫 まで解説します。
「投資のバランスってどう取ればいいの?」という疑問を持つ方に、実践的なヒントになれば嬉しいです。
個別株投資の魅力と現実:おさかなのリアル戦績
高配当株を選ぶ理由
投資信託(インデックス投資)は、市場全体に分散できるので長期的な資産形成に向いていて、リターンも平均的に安定しています。
「とにかく手間をかけずに資産を増やしたい」という人は、インデックス一本でも十分です。

じゃあ、なんでおさかなは高配当株もポートフォリオに入れているの?

理由はシンプルで、配当金が今の生活費を支えてくれるからだよ!
資産形成は「将来のためのお金」を積み上げる一方で、今すぐ使えるお金(キャッシュフロー)は減ってしまいます。そこで、高配当株を持つことで毎年の配当金が入り、将来の資産形成と今の生活の安心を両立できるんです。
さらに、インデックス投資は取り崩し(出口戦略)が難しいという声もあります。その点、高配当株なら売却しなくても定期的に現金が入るため、出口の一部を補う役割も果たしてくれます。
- インデックス投資 = 将来のための資産形成
- 高配当株 = 今の生活を支えるキャッシュフロー
2つを組み合わせることで、長期の成長と短期の安心感を同時に得られる。
保有銘柄と損益(2025年9月時点)
| 銘柄 | 購入金額(100株) | 評価損益 | 損益率 |
|---|---|---|---|
| 三菱商事 | 254500 | 91900 | 36.10% |
| 信越化学 | 470900 | -29200 | -6.20% |
| 三菱UFJ | 13845 | 90700 | 65.50% |
| NTT | 18780 | -2650 | -14.10% |
| オリックス | 320300 | 75200 | 23.50% |
| JT | 384700 | 91700 | 23.80% |
| サンドラッグ | 441600 | 17200 | 3.90% |
| アルフレッサHD | 231750 | -1350 | -0.60% |
📊 プラス銘柄もあれば、マイナス銘柄もある。これが「個別株の現実」です。
個別株に興味を持った方はまずは証券口座を準備しましょう。
※投資は自己責任です。
医療株を選んだ背景(体験談)
おさかなの妻は持病を抱えているため、医療費リスクを意識しています。その気持ちから、アルフレッサHDのような医療関連株を「応援投資」として保有しているのも特徴です。
もちろん、財務状況や将来性など株式投資で抑えるべきポイントも見て判断しています。
投資信託投資の安心感と成長性
「長期・分散・積立」が基本戦略
おさかな家の投資の柱は、インデックス投資信託。積立NISA・新NISAを活用して、毎月自動でコツコツ買っています。
<主な積立銘柄>
- eMAXIS Slim 全世界株式(オルカン)
- eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
- 楽天・全米インデックス(VTI)
- NASDAQ100インデックスファンド
ドルコスト平均法の効果
自動積立により、価格が高いときは少なく、安いときは多く買える「ドルコスト平均法」が効いています。
2024年1月〜2025年9月の新NISA口座全体の成績は +1,260,009円(+25.8%)と大きく成長。旧NISAのVTIも +50.4% と好調です。
ドルコスト平均法は効果あるの?という方はこちらの記事もあわせて読んでみてください。
▶︎ ドルコスト平均法の効果は本当?つみたてNISA実績で解説【資産600万円突破】
おさかな流!リスク管理とバランス戦略
1. 生活防衛資金の確保:生活費2〜3か月分(約80〜120万円)を現金で保持。
2. 分散投資の徹底:個別株・ETF・全世界株・米国株・NASDAQ100と幅広く分散。
3. 長期目線:「世界は長期で成長する!」の信念で一喜一憂しない。
4. 柔軟な積立額調整:収入減の時は月10万円→4万円に減額。でも「ゼロにはしない」。
5. リスク資産を厚めに:株式比率83%。30代なので日本平均(現金51%)より高リスク。
まとめ:あなたに合った投資バランスを見つけよう
個別株:高配当や大きな利益を狙えるが、銘柄選び次第で損失リスクもある。
投資信託:分散投資で安定成長、手間が少なく精神的にもラク。
おさかなは「両方を組み合わせる」ことでリスクとリターンを調整しています。
投資を考えているあなたも、まずは家計の見える化から始めてみませんか?
👉 [家計簿公開シリーズ]をチェックすれば、投資に回せる金額のヒントが見えてきます。
そして投資を始めるなら、[金融庁のNISA公式解説ページ]も一度読んでおくと安心ですよ。
おさかなはどんな風にNISA活用してるの?という方は、こちらの記事を合わせて読んでみてください。
▶︎ 【2025年版】NISAとは?初心者向け制度解説と、おさかな家が80万円の大出費を売却益で乗り切ったリアルな「出口戦略」
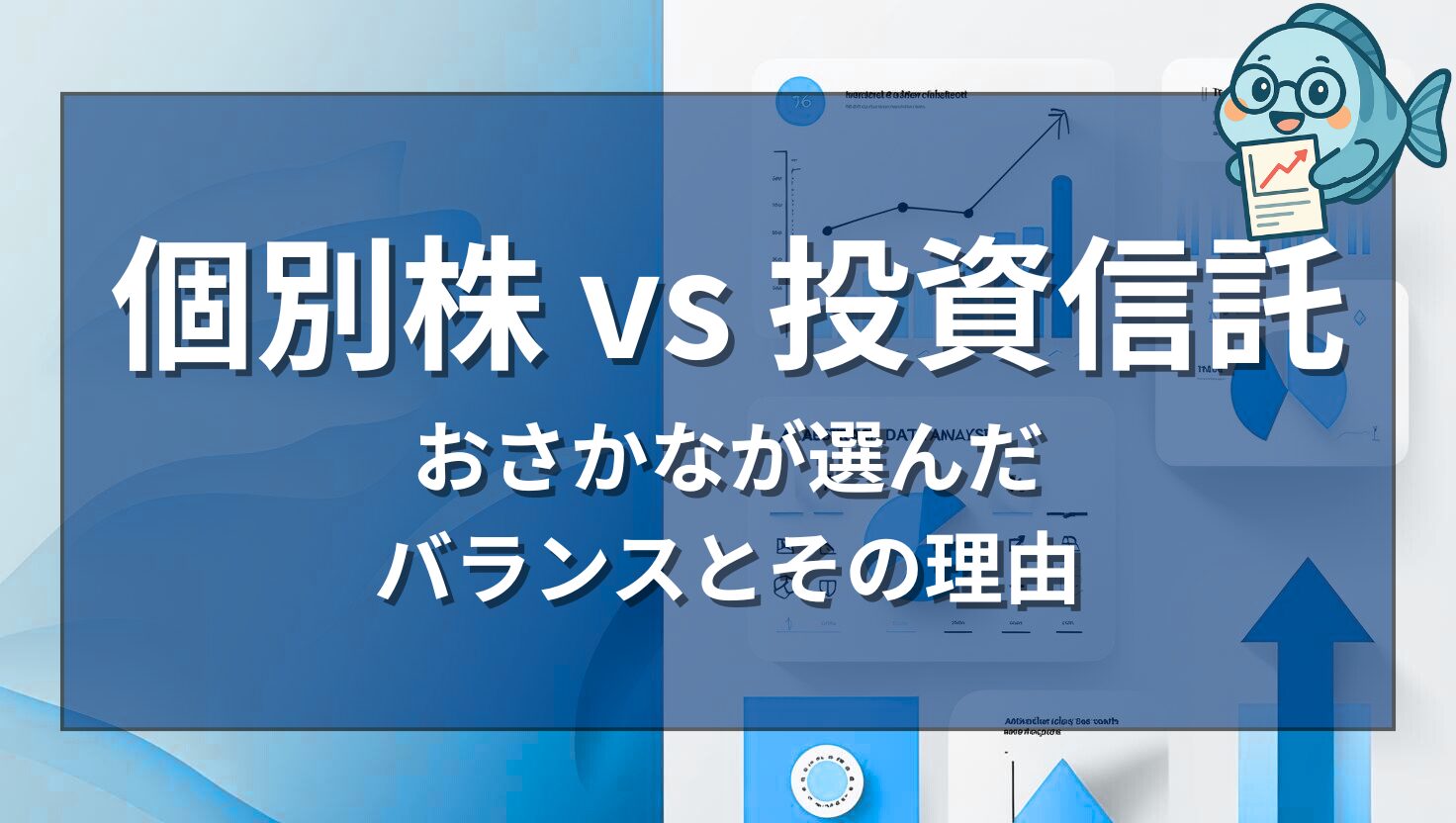
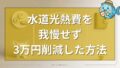
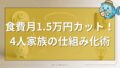
コメント