こんにちは!
地方で製造業しながら、夫婦共働きしている”おさかなパパ”です🐟

家計管理、うまくいってますか?
「貯金がなかなかできない・・」
「保険料が毎月バカにならない…」
「でも、みんな入ってるし、なんとなく不安で…」
…そんな気持ち、すごくよくわかります。
実はぼく自身、昔は周りに流されて、いろんな保険に入ってました。
でも、ある時ふと気づいたんです。

これ、本当に必要な保険なのかな…?
FP3級で学んだ“公的保険への理解”で、保険のムダに気づけた結果
▶ 夫婦で月々25,000円 → 月々2,000円に
▶ 年間で約24万円の節約に成功!
▶ その分を貯金やNISAにまわして、家計がどんどん安定!

保険とのよい付き合い方を工夫して、幸せ家族が増えたらいいな!
そんな想いで今回は、おさかなパパが「医療保険がいらない」と思った5つの理由と、実際にどう見直したのかを紹介していきます。
・家計の見直し、どこから手をつけたらいいか分からない忙しい共働きパパ・ママ
・医療保険に入ってはいるけど、「ほんとに必要なの?」とモヤモヤしている人
・毎月の保険料が高くて、家計が厳しい…と感じている人
・「安心のために入ってるけど、実は中身はよくわかってない…」という人
結論:医療保険は“いらない”ことが多い
もちろん、すべての家庭にとって「不要」と言い切れるわけではないです。
でも、制度と数字を知れば、「あ、意外といらないかも…」と感じる人は多いはず。
おさかなも数字を知ることが、最初のステップでした。
医療保険が不要と感じた5つの理由
① 公的保険で7割以上カバーされる
② 高額療養費制度で、どんなに高額でも上限あり
③ 入院は意外と短期間
④ 先進医療の利用率はごくわずか
⑤ 保険は“見えるリスク”だけに強い
① 公的保険で7割以上カバーされる
日本は「国民皆保険制度」で、ほぼすべての人が何かしらの健康保険に入っています。
医療費の自己負担額は原則3割負担なので、10万円の医療費でも実際の支払いは3万円程度。
さらに自治体によっては、子どもの医療費が中学生や高校生まで無料だったり、ワンコインで済んだりします。

おさかな家の住む地域も、子ども2人は無料!ありがたいです
「高い医療費に備えないとやばい!?」という思い込みは、まずここで崩れました。
② 高額療養費制度で、どんなに高額でも上限あり
たとえば100万円の医療費がかかった場合でも、年収500万円の家庭なら、高額療養費制度を使えば自己負担は月約9万円程度です。
「医療費100万円かかったら困っちゃう」と保険でたくさん備えていたけど、制度を使えば実はそんなに払わなくていい。
これを知ったとき、「医療保険はムダかも」と思いました。
年収によって自己負担額が変わるので、下記サイトでシュミレーションしてみてください。
▶︎参考:【協会けんぽ】高額療養費の簡易試算
③ 入院は意外と短期間
「でも半年とか入院したら…」と思っていたけど、ちゃんと数字と向き合ったら捉え方が変わりました。
厚労省「令和5年 患者調査」によると、
入院日数の実態は、全体平均で28.4日です。
しかし、年代別で見ると若年層はもっと短めです。
20〜24歳:平均13.1日
25〜29歳:15.5日程度
30〜39歳:21日程度
40〜49歳:28日程度
さらに、40代以下の約8割は、14日以内に退院しています。
僕たち子育て世代にとって、「長期入院→多額の出費」というのは、実はかなり少数派なんですね。
▶ 参考:厚生労働省「患者調査」
▶参考:OECD Health at a Glance 2023
④ 先進医療の利用率はごくわずか
「先進医療も不安だから…」と特約を付けていたけど、実際に使われているのは年間約26,000件。
日本の人口(1億2,000万人)からすると、利用率はたったの0.02%ほど。
さらに、先進医療は『保険適用できるほど確証が取れていない治療』なので、必ず有効とは限らないみたいです。
費用はかなりばらつきありますが、平均57万円前後。がん治療などで330万円。
おさかな家では「いざという時は、貯金で対応できる」と判断しました。
⑤ 保険は“見えるリスク”だけに強い
保険って、「病気」「ケガ」みたいな“見えるリスク”には対応できるけど、
- 子どもの急な学費
- 突発的な車の修理代
- 家電の買い替え
- 収入減少、失業
…こんな“見えないリスク”には対応できません。
だからこそ、「貯金」や「生活防衛資金」を持っておくことのほうが、実は守れる範囲が広いんです。
保険、見直しの3ステップ
(おさかな家の保険見直し結果)
| 項目 | 見直し前 | 見直し後 |
| 保険タイプ | 生命保険+医療特約 | 収入保障保険 |
| 月額保険料(夫婦) | 約24,000円 | 約2,000円 |
| 死亡保障額 | 3,000万円 | 1,000万円程度 |
| 削減額(年間) | – | 約24万円 |
ステップ1|現在の保険料を把握する
昔のおさかな家は、オプションもりもりで月2.5万円でした。
結婚してすぐ内容もよくわからず、周りから言われるがまま加入。
・妻:女性疾病、がん、入院特約など → 月9,000円
・自分:3000万円の死亡保障、入院保障付きの生命保険 → 月15,000円
合計24,000円以上!
「まぁ義母も勧めてくれたし、みんなも入ってるし、備えておけば安心かなぁ」くらいに思っていました。
でも、子どもが生まれて生活費が増える中、貯金ができない家計に危機感…。
「このままで本当に大丈夫なのかな?」
と不安になり、固定費削減を目指して、保険も本気で見直すことにしました。

あなたは、自身の保険料がいくらか把握してる?
ステップ2|必要保障額を計算する

まず初めにやったのは「必要保障額」の計算。
いきなり解約!ではなく、「もし”おさかなパパ”が突然いなくなったら、残された家族にはいくら必要なの?」を数字で出すことでした。

計算のやり方を調べるとFPさんが丁寧にまとめてくれてた!
現在の生活費 ✖️ 70% ✖️ 子供成人までの年数
さっそく、おさかなも計算・・・
1、現在の生活費:月34万円
2、住宅ローンは団信(※)で消えるので、ー7万円
3、子どもが成人するまで:約14年5ヶ月(173ヶ月)
4、必要保障額=27万円 × 70% × 14年5ヶ月(173ヶ月) ≒ 3270万円
必要なお金 ▶︎ 3270万円
※団信・・・団体信用保険(もしもの時(死亡・高度障害)に住宅ローンの返済が不要になる保険のこと)

あなたは万が一の時に必要なお金は、いくらだった?
ステップ3|公的制度・会社の保障を確認する
公的保険や会社の保障をしっかり計算してみると、意外と受け取れるお金がありました。
1.遺族基礎年金(月額10万以上)
2024年時点から、
・12年間1488万円(長男が成人するまで)
・2年間は202万円(長女が成人するまで)
合計1690万円
2.遺族厚生年金(概算40万/年)
14年(仮) 560万円
※子供が成人するまでと仮定
3.会社の共済保険
死亡時保障金 500万円
(必要なお金)3270万円 – (もらえるお金)2750万円 = (足りないお金)520万円

民間保険がないと、520万円不足しそう!
会社の保障は転職・失業リスクがあるので省いて考えると、1020万円の不足。
おさかなの死亡保障3000万円は、過剰すぎることが明らかになってしまいました。

あなたの環境や状況で、使えるお得な制度があるかも!?
公的保険で補える分を把握しよう。
不足を補える保険を選定
見直しの結果、加入したのは「FWDの収入保障保険」。
・自分:月々1,038円 → 年金月額8万円(50歳まで)
・妻:月々1,028円 → 同条件
必要なお金(リスク)は子供の成長とともに減っていくので、不足金額1000万円を埋められる掛け捨て保障を選択しました。
これだけで安心はキープしつつ、月2万円以上の節約に成功!
もちろん、医療保険を「安心のために持っておきたい」という考え方もあります。
どちらも間違いではありません。
だからこそ「感情」でなく「数字」で判断することが大切だと、おさかなは感じます。
まとめ|医療保険より「貯金」を優先しよう
・ 公的保険や制度で、医療費の大部分はカバーできる
・ 医療保険は“安心料”と割り切って、本当に必要な保障だけに
・ 固定費を見直して、貯金や教育資金に回すと家計がぐっと楽に!

意外と公的保険で6〜8割はカバーできている可能性もあるよ!
保険は『安心』を買うからこそ、実態が見えなくて買いすぎていることにも気が付きにくい・・・。
不安だから…で入り続けるのではなく、制度と数字を理解して「納得して選ぶ」ことが、これからの時代には大事だと思います。
数字にして客観視してみましょう。
まずは、あなたの保険料が「過剰なコスト」になっていないか、ぜひチェックしてみてください!
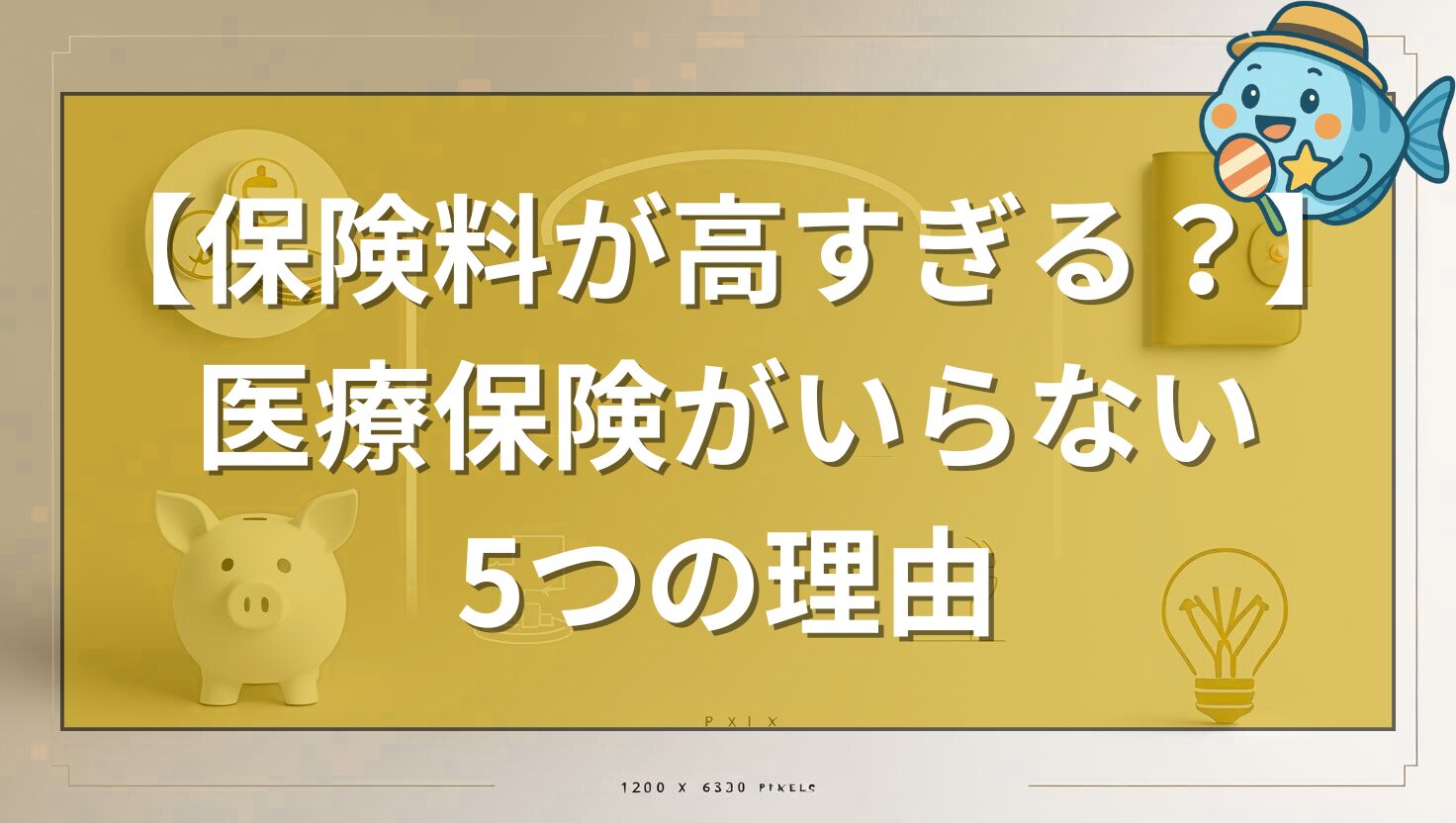
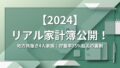
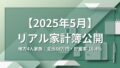
コメント